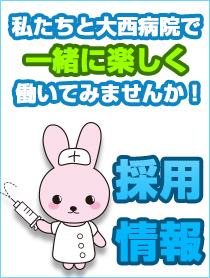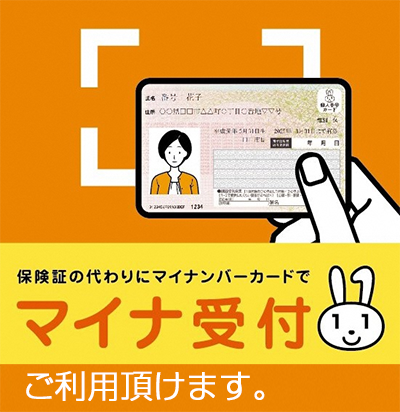認知症窓口
開設以来「患者様を大切にする」をモットーに認知症サポート医による診断治療を行なっています。思い当たることはありませんか?
- 同じ事を何度も言ったり、質問したりするなど物忘れがひどい
- 料理など家事の段取りが悪くなった
- 慣れた道でも迷う事がある
- お金などを盗られたと騒ぐ
- ひとりになると怖がったり寂しがったりする
- 趣昧や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった
- etc...
専用回線
TEL:087-865-3360 / FAX:087-865-3365受診曜日時間 (日曜・祝日・年末年始休診 12/30~1/3)
初診・最終診察日より3ヶ月以上経過している方は予約が必要です。
来られる前に必ずお電話下さい。(再診の方は必要ありません。)
(かかりつけの病院がある方は紹介状が必要となります。
頭部CT・MRIを撮られている方は画像もお持ち下さい。)
初診は2時間位かかります。
| 曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 |
9-12 |
9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 休診 |
| 午後 |
13-17 |
13-17 | 休診 (相談のみ可) |
13-17 | 13-17 | 休診 | 休診 |